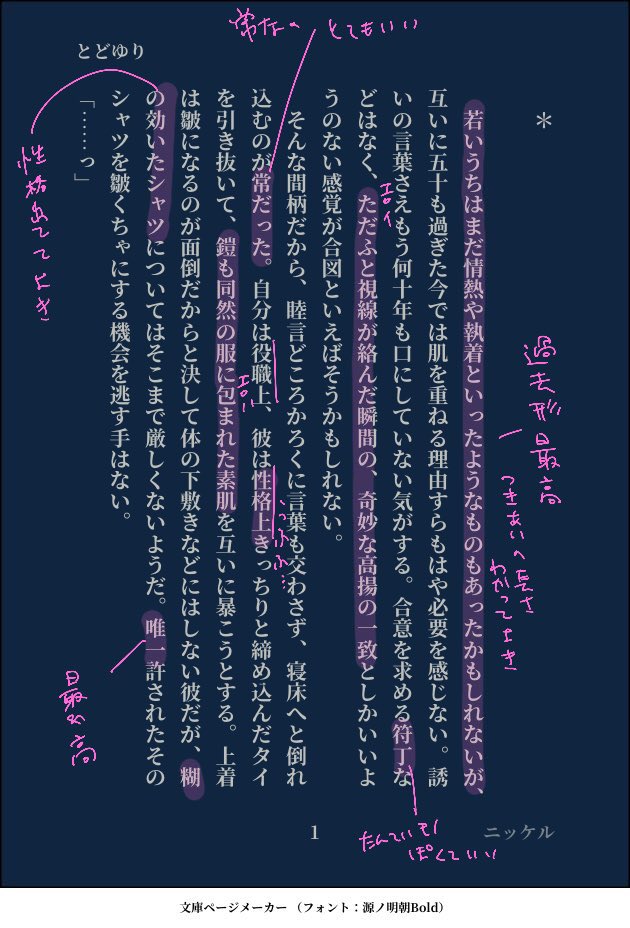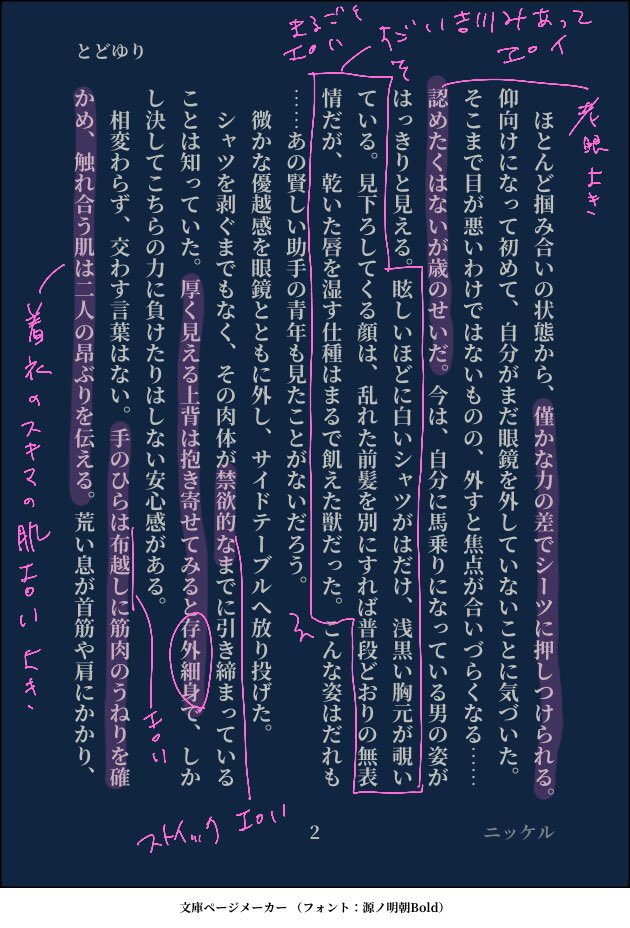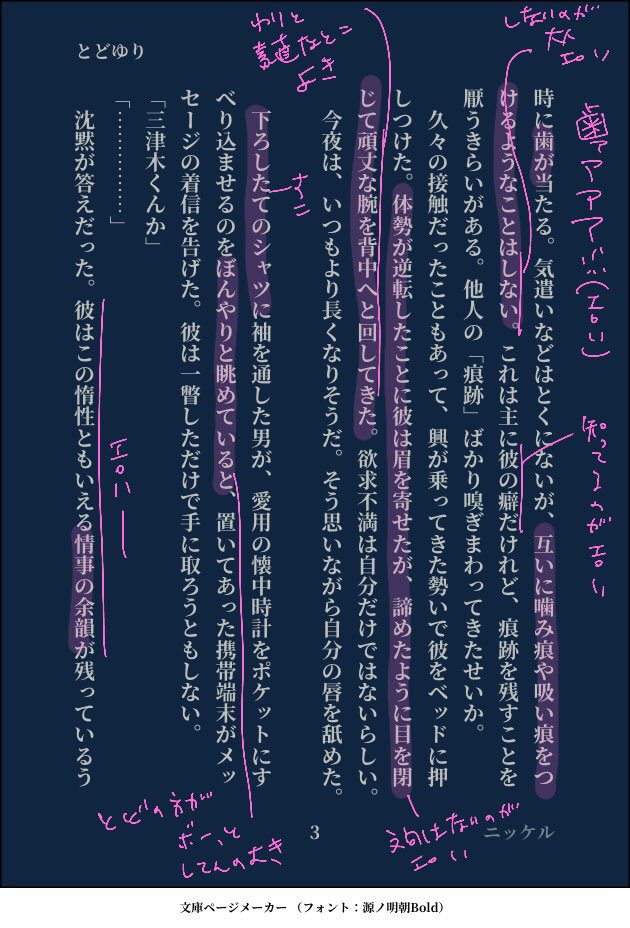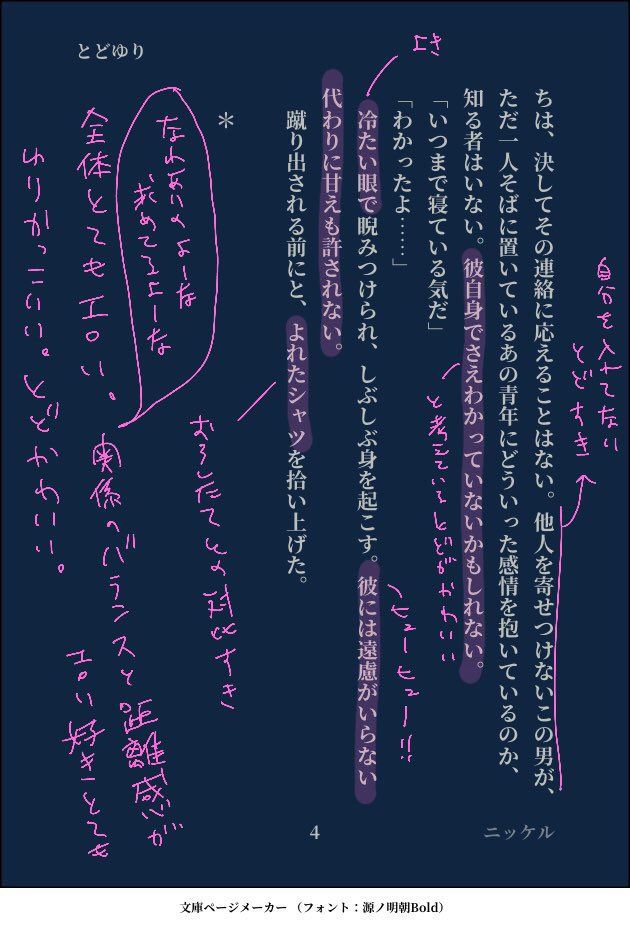【SS】由利と等々力「馴染」
衝動的に書いたやつ。いつもより「冗長さ」を意識しました。
馴染
若いうちはまだ情熱や執着といったようなものもあったかもしれないが、互いに五十も過ぎた今では肌を重ねる理由すらもはや必要を感じない。誘いの言葉さえもう何十年も口にしていない気がする。合意を求める符丁などはなく、ただふと視線が絡んだ瞬間の、奇妙な高揚の一致としかいいようのない感覚が合図といえばそうかもしれない。
そんな間柄だから、睦言どころかろくに言葉も交わさず、寝床へと倒れ込むのが常だった。自分は役職上、彼は性格上きっちりと締め込んだタイを引き抜いて、鎧も同然の服に包まれた素肌を互いに暴こうとする。上着は皺になるのが面倒だからと決して体の下敷きなどにはしない彼だが、糊の効いたシャツについてはそこまで厳しくないようだ。唯一許されたそのシャツを皺くちゃにする機会を逃す手はない。
「……っ」
ほとんど掴み合いの状態から、僅かな力の差でシーツに押しつけられる。仰向けになって初めて、自分がまだ眼鏡を外していないことに気づいた。そこまで目が悪いわけではないものの、外すと焦点が合いづらくなる……認めたくはないが歳のせいだ。今は、自分に馬乗りになっている男の姿がはっきりと見える。眩しいほどに白いシャツがはだけ、浅黒い胸元が覗いている。見下ろしてくる顔は、乱れた前髪を別にすれば普段どおりの無表情だが、乾いた唇を湿す仕種はまるで飢えた獣だった。こんな姿はだれも……あの賢しい助手の青年も見たことがないだろう。
微かな優越感を眼鏡とともに外し、サイドテーブルへ放り投げた。
シャツを剥ぐまでもなく、その肉体が禁欲的なまでに引き締まっていることは知っていた。厚く見える上背は抱き寄せてみると存外細身で、しかし決してこちらの力に負けたりはしない安心感がある。
相変わらず、交わす言葉はない。手のひらは布越しに筋肉のうねりを確かめ、触れ合う肌は二人の昂ぶりを伝える。荒い息が首筋や肩にかかり、時に歯が当たる。気遣いなどはとくにないが、互いに噛み痕や吸い痕をつけるようなことはしない。これは主に彼の癖だけれど、痕跡を残すことを厭うきらいがある。他人の「痕跡」ばかり嗅ぎまわってきたせいか。
久々の接触だったこともあって、興が乗ってきた勢いで彼をベッドに押しつけた。体勢が逆転したことに彼は眉を寄せたが、諦めたように目を閉じて頑丈な腕を背中へと回してきた。欲求不満は自分だけではないらしい。
今夜は、いつもより長くなりそうだ。そう思いながら自分の唇を舐めた。
下ろしたてのシャツに袖を通した男が、愛用の懐中時計をポケットにすべり込ませるのをぼんやりと眺めていると、置いてあった携帯端末がメッセージの着信を告げた。彼は一瞥しただけで手に取ろうともしない。
「三津木くんか」
「……………」
沈黙が答えだった。彼はこの惰性ともいえる情事の余韻が残っているうちは、決してその連絡に応えることはない。他人を寄せつけないこの男が、ただ一人そばに置いているあの青年にどういった感情を抱いているのか、知る者はいない。彼自身でさえわかっていないかもしれない。
「いつまで寝ている気だ」
「わかったよ……」
冷たい眼で睨みつけられ、しぶしぶ身を起こす。彼には遠慮がいらない代わりに甘えも許されない。
蹴り出される前にと、よれたシャツを拾い上げた。
了
おまけ:
アルカリと交換でやった「どこがどうよかったかを書き込む」遊びがおもしろかったので……すごく頭が悪くなります。